常備自衛官とともに日本の防衛力を支える予備自衛官
防衛省・自衛隊の防衛力を最大限に機能させるためには、人的基盤の強化は欠かせないが、少子・高学歴化の進展や企業などによる大学生の採用活動の早期化など、自衛官の募集・採用を取り巻く環境は厳しさを増している。
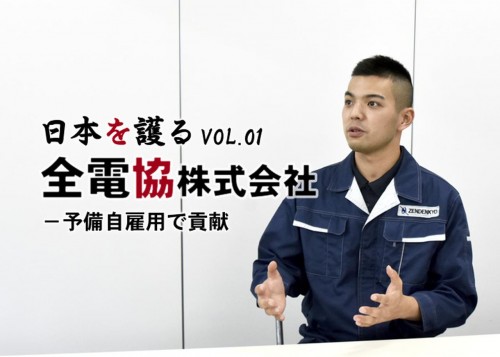
防衛省・自衛隊の防衛力を最大限に機能させるためには、人的基盤の強化は欠かせないが、少子・高学歴化の進展や企業などによる大学生の採用活動の早期化など、自衛官の募集・採用を取り巻く環境は厳しさを増している。
一方、国家の緊急事態にあたっては大きな防衛力が必要となるが、その防衛力を日頃から保持するのは効率的ではない。そこで防衛省では、平時は常備自衛官の防衛力で対応し、有事の際は急速に防衛力を増強できるよう、「予備自衛官等制度(予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補の3制度)」を設けている。
予備自は普段は企業の一員として勤務しつつ、有事の際には自衛官として災害招集などに貢献する。年間で定められた日数の訓練に参加することが義務付けられているなど、予備自の維持は志願者の意思だけではなく、雇用する側の企業努力も不可欠だ。実際に予備自を雇用する企業ではどのような取り組みを行っているのか、今回は「予備自衛官等協力事業所」として防衛省に認定を受けた企業に取材を行った。
東京都日本橋茅場町に本社を構え、高圧受変電設備(キュービクル)の保安管理業務を行っている全電協株式会社では、現在4人の従業員が予備自として活躍している。顧問を含め自衛官OBが16人も所属しているというのも、同社がいかに自衛隊や予備自に対して理解が深いのかがうかがえる。予備自の一人である小堀風神(ふうじ)さんも元自衛官だ。
──入社の経緯について教えてください。
小堀 高校卒業とともに自衛官候補生として空自に入隊し、5年の任期満了時に退職して弊社に入社しました。入社の経緯としては、就職援護による合同企業説明会の弊社ブースで話を聞いたのがきっかけです。
自衛隊でドローンパイロットのライセンスを取得していたので、その技術を生かせる業務に就きたいと思っていたところ、弊社のブースにドローンが展示してあって興味を持ちました。ちょうどドローン操縦者の求人で、今後はドローンを使った技術を事業化する予定だと聞き、「ここしかない!」と思い応募しました。
──自衛隊を辞めた後もなお、予備自を志願したのはなぜだったのでしょうか。
小堀 もともと、自衛官を辞めた後も即自として活動を続けたいと思っていたのですが、そんな時に上司から「予備自で一緒に訓練をしよう」と誘いがあったのです。
定年退職以外で自衛隊を辞める人は、基本的に自衛隊が嫌になって辞めるのがほとんどだという印象が強かったので、自衛隊を退職してなおこんなに熱意がある人がいるんだと驚きと感銘を受け、「やってみよう!」という気持ちになりました。
5年間自衛官として活動してきたので、その経験を生かせればと。業務の都合上、現在は予備自ですが、当初は即自で活躍したいと思っていました。
──訓練招集など予備自の活動と業務の両立はできていますか。
小堀 弊社では予備自に対する理解が深く、訓練招集をはじめ有事の際に派遣招集がかかった場合も快く送り出してくれるサポート体制が整っています。予備自を推奨してくれる企業というのはなかなかないのではないかと思います。
というのも、自衛隊での就職援護支援の際、求人票に予備自を推奨している旨が記載されている企業もあるのですが、実際は『5日間まとめて訓練に行くのはやめてほしい…』や『実際に災害招集がかかって出頭されると困る…』などと言われるケースがかなり多いと聞いています。
また、予備自の年間5日間の訓練は2日間と3日間に分けて参加する人も多いのですが、弊社では5日間連続で参加できる上、有休などを使わず業務の一環として参加できるので、すごく働きやすい環境ですね。できれば即自として活動したいのですが、今は資格を取ることが目標なので、勉強を優先しています。
──小堀さんは現在はどのような業務を行っているのでしょうか。
小堀 保安管理部保安工務第一課員として、ドローンを用いた点検方法の検討や事業化の準備を進めています。例えば、メガソーラーと呼ばれる大規模な太陽光発電システムのパネルの点検などにドローンを活用しています。
メガソーラーはとにかく広大なため、人手で1枚ずつ点検していては途方もない時間と労力がかかってしまいます。そこで、暗視カメラを搭載したドローンで俯瞰(ふかん)してチェックしています。太陽光パネルに異常をきたしている場合はだいたい熱を帯びるので、赤外線カメラで検知することができるのです。

予備自として活動する小堀氏
──そのほか、自衛隊での経験が業務に役立っていることはありますか。
小堀 新入社員教育の際に私が就業規則などの説明をしているのですが、自衛隊では教育の職種に就いていたこともあり、人前で話す機会も多かったので、それが生かせられていると感じます。もともと、人に何か教えることが好きなんです。
──現在は電気主任技術者試験(電験三種)合格に向け勉強をされているそうですね。
小堀 電験三種合格に向け、現在は毎日夜間の専門学校に通っています。通学の移動時間を考慮していただき、定時よりも1時間早く上がらせてもらうなど会社が支援してくれるので助かっています。
資格を取ることは大変ですが、電験三種の合格はゴールではなく最低条件。弊社に入社し、高圧受変電設備の保安点検業務がどれだけ尊いものかを学ぶことができました。
三種に合格したら次は二種を目指すなど、もっともっと勉強して電気に関する知見を深めていく必要があると思います。
──これから予備自を目指したい人へメッセージをお願いします。
小堀 私はまだ予備自としての災害招集経験はありませんが、声がかかったらいつでもすぐに行ける準備はしてあります。
普段、企業に勤めながらも予備自に興味を持たれている方もいると思いますが、なかなか一歩を踏み出せない人も多いのではないでしょうか。でも、その一歩を踏み出すことによって救うことができる命があります。私のように若い人の力が必要とされているので、勇気を出して一歩踏み出していただければ嬉しいです。
全電協では予備自の雇用について、どのような取り組みや教育を行っているのか、総務課課長の吉原方人(かたんど)氏と全電協安全衛生事務局長の近藤力三(りきぞう)氏に話を聞いた。両氏とも防大出身の元自衛官だ。

総務課課長の吉原氏(左)と全電協安全衛生事務局長の近藤氏(右)
──元自衛官や予備自の雇用は創業時から取り組んでいたのでしょうか。
吉原 創業当初は元自衛官や予備自の雇用を積極的に行っていたわけではありません。意識的に自衛官のOBを採用することになったのは、元陸将の松島悠佐(ゆうすけ)顧問の影響によるところが大きいでしょう。
松島顧問は平成7年の阪神淡路大震災の際に中部方面総監として災害派遣の最高指揮官として指揮を執っていたこともある人物で、自衛隊退職後に開催していた「松島塾」という勉強会に、弊社の代表取締役・山口社長が参加したのがきっかけです。
系列会社の信光グループ主催による「安全衛生大会」で登壇する代表取締役の山口氏
そこで山口社長が松島顧問の考えに感銘を受けるとともに自衛隊にも関心を持ち、その後、弊社の顧問としてお迎えした経緯があります。それから、地本の援護課にコンタクトを取り、退職自衛官の求人を募るようになりました。
元自衛官の人材は、厳しい訓練を経験してきたこともあり、若年層でも組織における規範意識などがしっかりしている人が多い。人材をゼロから教育する必要がないので、任期制自衛官など若年退職者の応募は弊社も大歓迎です。やる気と興味さえ持ってくれれば、技術面は入社してからでも磨けますので。
近藤 元自衛官は集団生活に慣れているという部分も大きいと思います。学校を出たばかりの若い人に、時間の厳守など社会の規律を一から教えるのは時間がかかるので難しいです。同世代の人と比較すると、あいさつの仕方一つとっても全く違いますね。元自衛官は優秀な人材が多いです。

元自衛官の人材について語る吉原氏
──予備自の雇用については企業の理解や努力も不可欠だと思いますが、会社としてどのような取り組みを行っているのでしょうか。
吉原 弊社では自衛官OBの採用と併せ、予備自の雇用にも積極的に取り組んでいます。もちろん、個人の意思を尊重することが前提なので、入社した全員を勧誘するのではなく、元自衛官をはじめ、予備自の活動に興味がありそうな人に個別で声をかけたり、地本からいただいた予備自衛官等制度のポスターやパンフレットなどを社内に掲示したりしています。その効果もあって、元自衛官ではない女性従業員が予備自補に志願してくれました。数回応募したにもかかわらず採用には至らなかったのですが、チャレンジしてくれた気持ちはうれしいですね。
近藤 社長の自衛隊に対する理解が深いので、予備自に関しても本人さえ希望すれば会社ができる限りサポートしています。おかげさまで予備自衛官等協力事業所として認定を受けました。
現在は予備自だけですが、希望者がいれば即自も歓迎します。現場としては年間30日間という訓練に参加するのは厳しい部分もありますが、周りの人間がカバーする体制が整っています。
災害はいつ起きるのかわからないからこそ、予備自を雇用する側の企業としては、いつでも対応できるような体制を整えておくことが大切なのです。

即自の雇用も歓迎すると話す近藤氏
電気設備の保安管理業務は電気主任技術者の資格が必須となるが、試験に合格しなくとも資格を取ることができるという。それは「電気事業法の規定に基づく電気主任技術者認定校」を卒業するという方法だ。認定校を卒業後、定められた期間の実務経験を積み、産業保安監督部に申請して審査を通過すれば、電験三種の資格を取得できる。
前述の小堀氏の話でも触れたが、全電協では従業員が電験三種の資格を取れるように認定校の専門学校に通えるための支援をしているという。
──電験三種合格のために会社ではどのようなサポートを行っているのでしょうか。
吉原 元自衛官でも一般の方でも、工業高校や専門学校で電気関係の勉強をしてきた人が求人に応募してくれればありがたいですが、そういう方は稀です。小堀のように興味とやる気があっても、電気の知識がない者が働きながら独学で勉強して電験三種の試験に合格することはなかなか難しい。
そこで、弊社では電験三種の資格を取得できるよう、終業後に夜間の専門学校(認定校)へ通うことも推奨しており、通学の際は勤務時間を1時間短縮するなど会社としてもできる限りサポートしています。
現在は専門学校の学費は自費となっていますが、金銭面でも従業員の負担を軽減できるよう奨学金制度などを検討しています。

全電協では、資格を取得するためさまざまな研修が行われている
吉原 私たちが汗をかくことが電気の安定供給につながり、社会貢献にもなるので、すごくやりがいのある仕事です。仕事をしながら実務経験が積めるのもメリットです。社会貢献にもなり、一生モノの技術も身に付く、そして頑張っただけ収入の増加につながる仕事です。
また、資格があり健康であれば長く続けられる仕事でもあるため、80代でも現役で活躍している者が何人もおります。
若い方は資格がなくともやる気さえあれば経験を積んで資格を取ることもできますので、電気設備の保安管理業務や予備自に興味を持った方はぜひ、当社で一緒に働きましょう。

東京・日本橋茅場町の本社ビル
全電協株式会社
〒103-0025
東京都中央区日本橋茅場町2-1-13
03-3808-2411
https://www.zendenkyo.co.jp/